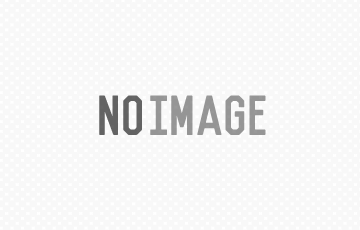フナムシの特徴
フナムシの体調は最大5cmほどの大きさのものもいますが、大小さまざまです。見た目は、ゴキブリやダンゴムシに似ていると言われています。体は平たい形をしており多くの節にわかれていて、7対の歩が生えています。(計14本)頭部には長い触覚と大きな複眼。尾の部分は2つに枝分かれした脚が1対あります。色は光沢のある黒色と淡い黄色のまだら模様のものが多く、夜は昼に比べ体色がコーヒー色のような茶褐色に変化します。
フナムシの生態と生息地
ご存知のようにフナムシの動きは非常に敏捷で、自分の体よりも大きな生き物が現れるとすぐさま一目散に岩陰に逃げ込みます。そのため、捕獲することは、かなり難しいと言われています。
フナムシは泳げるの?
フナムシは海岸近くに生息していると言う話をしましたが、その割りには、海中で見かけることはほとんどありません。それはなぜでしょうか?実は、フナムシは、水中に長時間いると溺れて死んでしまうのです。フナムシは通常、海に入ることはなく、たまに誤って海に落ちた時は、多少泳ぐこともできますが、基本的には、水中では生きることができません。
フナムシはどこに分布しているの?
フナムシは危険?フナムシの天敵はどんな生物なのか?
人間も、知らない間に噛まれて痛みを感じることがありますが、毒性はありませんのでご安心ください。フナムシの天敵は岩ガニ、アカデガニなどですが、海に落ちた場合は魚のエサになることもあります。これもフナムシの生態を知る上では必要なことではないでしょうか?
フナムシのメスと赤ちゃん
さらに、フナムシの生態をさらに詳しく調べていくと、こんなこともわかりました。産卵時期のメスの腹部には卵を抱える保育嚢(ぶくろ)があり、その嚢(ふくろ)で卵を保護しています。卵は、最初は透き通った橙色ですが、やがて黒く変化していきます。
孵化する幼体はとても小さいですが、親と同じ体形をしており孵化した後もしばらくはメスの保育嚢(ぶくろ)に掴まって生活をしています。
フナムシの赤ちゃん
この時期にメスを捕獲すると保育嚢(ぶくろ)の中からフナムシの赤ちゃんがぞろぞろと飛び出して出てくることもあるそうです。フナムシの赤ちゃんはゴマ粒より少し大きいぐらいで色はやや白っぽい色をしています。フナムシの寿命は3~4か月、長くても6か月で、意外にも短いと思いませんか?
フナムシは釣りの餌として利用されている
フナムシで釣り
フナムシで釣れる代表的な魚は、さまざまで、カサゴ、イシダイ、メジナ、アジ、ハゼなどの餌としても使われています。釣りをする人は、フナムシをエサとして使うことは良くあるようで、釣り餌として非常に優秀と言えます。エサ代が抑えられる分、捕獲するにちょっと苦労しそうですが、これほどの大型の魚が釣れるとなると、これは釣りをする人にとってはかなりの利用価値があることがわかります。
フナムシで釣りの仕掛けをつくる
釣りをする人が実際に、フナムシをエサとして利用する際に、ペットボトルなどを使って簡単にフナムシを捕獲する方法もネット上に紹介されていたりします。この方法だと仕掛けてから30分程度でフナムシを捕獲することが可能なようで、釣りをする人にしてみると、なくてはならない存在として重宝がられているようです。
フナムシは食べられる?味はどんな味がするの?
食感はカニやエビににている
脚の付け根のわずかな筋肉にはわずかに甲殻類系の風味が感じられるそうです。甲殻類と言えばカニやエビもそうですが、それらと同じ食感が本当に味わえるのかは、いささか疑問です。
フナムシの食べ方
ここまで行くとフナムシを愛してやまない人しかできないことですが、フナムシの調理方法を少しご紹介します。まず、下処理は必須。(においとりと殺菌のためだそうです)フンをすべて出してあげる必要があるため時間と手間がかかります。
フナムシの味
揚げる、ゆでる、炒める、焼くなどの調理法はあるようですが、基本的にはとてもまずいと、食した99%の人が答えています。臭いは内臓が非常に臭く、磯の臭みを凝縮したような味で、中には排泄物のような臭いがすると言う話もあります。どれくらいの人がフナムシを食しているかはわかりませんが、いやはや、これを試す勇気は私にはありません。どなたか試した方がいらっしゃいましたらぜひとも感想をお待ちしております。
フナムシとゴキブリの違い
前途したように、フナムシは容姿や動きでゴキブリに似ていると言われるのはお分かりいただけたかと思いますが、はたして本当にゴキブリと同類なのか?と言うと実はいくつか違う点があることがわかっています。
具体的にはどう違うのか?
フナムシとゴキブリ違いは、昆虫と甲殻類(節足動物)の違いです。ゴキブリが昆虫であるのに対し、フナムシは甲殻類(節足動物)に相当します。それに、フナムシには羽がありませんが、ゴキブリには羽が生えています。ただ、フナムシのエサは藻類や魚の死骸を食べて生きており、一方、ゴキブリは動物の死骸やフンなどを食べていきていると言う点ではどちらも似ていますね?また、フナムシは集団で行動するのに対し、ゴキブリは単独で行動するため、生態についても多少違いがあるようです。
フナムシは汚い
また、どちらが汚いのか?と言う点では、不衛生な場所で生きているゴキブリに比べ、フナムシは海辺にすむ生物なので塩分に弱い菌が無い分、細菌性は少ないようです。ここまでフナムシとゴキブリの違いを詳細に書きましたが、書いている本人が言うのも何ですが、正直、書きながら鳥肌が立っている状況です。結局のところ、どちらも気持ち悪さは変わらないと、言う結論になり、違いを調べてもあまりピンときません。
フナムシはかわいい
これだけ、気持ち悪さを述べておいて、いきなりかわいい?ってどういうこと?一部の人からは、こんなフナムシでもかわいいと思えるところがあるようです。海辺の岩陰から勢いよく「サーッ」と走り去る姿もじっくり観察してみると意外にかわいらしい顔つきで憎めない魅力があると言う方もいらっしゃいます。
フナムシの飼育
フナムシに魅了されて飼育する人もいるようで、自分で捕獲することができない場合はわざわざ購入して飼育も可能だそうです。恐らく通常のペットショップでは販売していないと思いますが、稀に販売しているところもあるようです。
具体的な飼育方法
フナムシを飼育するのにはサンゴや砂、川砂を敷き詰めて隠れ場を確保するレイアウトにして飼育ケースは風通しのよい場所、直射日光があたらない場所を選ぶ必要があります。水分補給はエサから摂取するだけではたりないため、水場を設けたり、塩水を霧吹きで吹きかけたりするなど結構の手間をかけて世話をする必要があるようです。