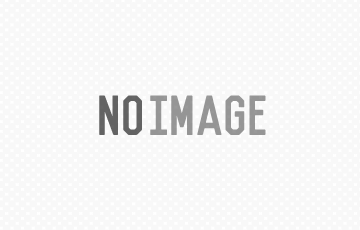カマツカの生態、特徴
カマツカはどんな魚?
カマツカはコイ目コイ科に分類され、成魚は15㎝から20㎝ほどの細長い体をしています。ほとんど泳ぎ回ることなく、川底でじっとしています。下向きについた口が特徴で、川底を這って進みながら砂と一緒に水生昆虫を食べて、エラから砂だけ吐き出します。
臆病なカマツカ
おとなしい性質でとにかく臆病です。外敵が近づいたり驚くと砂に潜ってしまい、目だけ砂から覗いていることから別名スナホリとも呼ばれています。飼育すると、人が水槽の前を通るだけでもパニックになることもあるので、慌てて水槽に身体をぶつけてしまい、ゴツンと大きな音に飼育側が驚かされることもあります。
カマツカの生息地、分布
カマツカを探そう
カマツカの生息地は岩手、山形以南の本州、四国、九州に分布。主に中流の川底や湖の岸近くの砂礫底など、胸びれを広げて水底にじっとしています。まれに用水路にもいたり、古くから日本の川で親しまれています。
底モノ
カマツカの生活圏は川底です。水面近くの高層や中層などで活発に泳ぎ回ることなく、川底で暮らす魚を総称で底モノと呼びます。水面から川底が見えるような透明度の高い川であっても、淡褐色の体が川底に擬態するので簡単には見つけられません。
カマツカの旬、時間帯
旬は春から初夏
カマツカの旬は3月から4月頃。その後5月から6月に繁殖期をむかえて、夕方から夜間にかけて産卵します。釣りは3月から12月によく釣れることから、およそ一年を通して日中に比較的よく見られます。
カマツカの繁殖
繁殖期に入ると、川が浅く流れが緩やかなところに産卵します。産んだ卵は川砂に埋めて隠すことがあります。水温が20℃ぐらいなら一週間ほどで孵化しますが、人口繁殖はとても難しく、水槽内の卵を混泳魚に食べられてしまう場合が多いので、繁殖に挑戦したいなら単独水槽を用意しましょう。
カマツカの釣り方
カマツカは採取困難?
自然下では水生昆虫も食べるカマツカ。雑食性なので、釣りはミミズを餌にした、ぶっこみ釣りが有効です。ただし、なかなかヒットせず根気が入ります。手網を使って捕獲する方法もあります。この場合、カマツカに近づきすぎてしまうと怖がって逃げてしまいます。動きが素早いので、逃げるカマツカを手網ですくい上げるのは難しいと言えます。
カマツカの捕り方
手網
手網でカマツカを捕まえるには、カマツカが居そうな場所を網でゆっくり砂ごとすくい上げると、砂と一緒にカマツカが網にかかることがあります。カマツカの体は淡褐色のため、水面から探してもピンポイントでは見つけにくいですが、一度砂に潜ると微動だにしないので、そのまま状態ならあっさり捕獲できます。
薬浴
カマツカなど採取した川魚には、有害な病原菌や寄生虫を持っている可能性が高いです。メチレンブルーなどの薬で2,3日薬浴させます。すでに他魚を飼育している水槽へカマツカを混泳させる場合は、特に感染の危険があるので必ず薬浴を行いましょう。稚魚など体力に不安があるならば無理せず様子をみます。
カマツカの料理
味わい
カマツカは鱗が細かく硬いので、あらかじめ取り除いてから料理します。白身でクセがなく、身が引き締まっていて全国各地で食べられていました。主に滋賀の琵琶湖周辺で流通されていて、料理は素焼き、天ぷら、煮つけなどが一般的。お刺身のような生食は寄生虫の危険があるので避けましょう。
カマツカ料理の減少
昔から日本に親しまれ、食卓にも並ぶことが多かったカマツカ料理ですが、現在はごく一部の地域で食べられるのみになりました。天然のカマツカを捕らなくても手軽に食用魚を購入できることや、川や清流など川魚の棲みかが奪われてしまった要因も考えられます。
カマツカの飼育必需品
淡水アクアリウム
カマツカを含めた淡水魚の飼育に必要な物を揃えましょう。水槽、照明、ろ過装置(フィルター)、ろ材、水槽クーラー、ソイル(底砂)、エアレーション、水温計、プロホースなど。カマツカにとって底砂は必須ですが、エアレーションは水質に敏感なので酸欠にならないように追加も用意があれば心強いです。
カマツカの飼育準備
底砂
カマツカにとって底砂は大変重要です。川底を這って採餌する習性や、とにかく臆病なので隠れ場所になる底砂は欠かせません。おすすめは田砂か川砂です。丸みと適度な細かい粒の底砂であれば、カマツカの体を傷つける心配もありません。水槽に入れる前に、しっかり洗って、乾燥させてから使用すると汚れが入らず安心です。
水槽
カマツカは水槽の掃除をしてくれるタンクメイトとして飼育される場合がほとんどです。苔や餌の残飯をきれいに食べてくれる掃除屋。おとなしい性格なので混泳もできます。混泳させる場合は、カマツカが他の魚に攻撃されないように流木や岩、土管のような隠れ場を用意します。水槽の大きさはカマツカの成長を考えて最低でも60cm幅は必要です。
水槽の立ち上げ
まず水を準備します。水道水に水質調整剤を使ってカルキ抜きします。購入した水槽は、一見きれいに見えても汚れているので洗います。あらかじめ準備した底砂を、3cmから4cmぐらい敷き詰めます。ゆっくり水を注いだらフィルターを回して水温が20℃から27℃になるように保ちます。そのままの状態で2日間、水を巡回させてから移します。