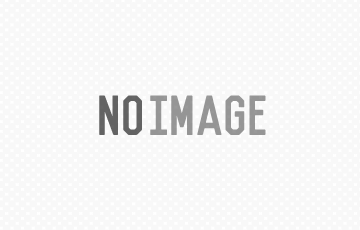サバフグの生態について
ここでは、そもそもサバフグとはいったいどのような魚なのかについて、その基本的な情報と大まかな生息域を説明していきます。サバフグを初めて聞いた、どこで釣れば良いのかわからないという方は必見です。
サバフグの基本的特徴
名前からも分かる通り、サバフグはフグ科フグ目に属するフグの一種です。体長はおおよそ15センチメートルほどで、一口にサバフグと言っても日本産だけで7種ほど存在します。また、地方名も様々で、徳島県ではアオシマと呼ばれています。その中でも、シロサバフグとクロサバフグとは生息個体数が多い事で有名です。サバフグは、無毒のものと有毒のものがあり頻繁に事故を引き起こしています。
サバフグの分布
サバフグは生息域の広い魚です。その生息域は、インド洋や太平洋全域において、その存在が確認されています。日本においては太平洋側全域において、北は東北、南は九州を超え更に南に進んだ海域においても見つけることが可能です。サバフグを見つけるためにはとにかく太平洋側に行くと良いでしょう。
クロサバフグについて
食用として広く知られているクロサバフグという種類に関して、重点的に話をしていきます。簾路サバフグの基本的な情報や外見に関する事だけでなく、クロサバフグの中でも有毒のものがいるといった知識を記していきます。
クロサバフグの基本的な特徴
クロサバフグはサバフグの中でも、白サバフグと同様に食べることができます。体長は最大で35センチメートルにも成長します。太平洋側の海においても沖合に生息していて、その生活は群れを成して営んでいる。尾びれや背びれは黒く、腹びれの辺りが白いのが特徴です。
有毒のクロサバフグ
クロサバフグは確かに食用ですが、その体内には毒を持っているので容易に食べようとするには注意が必要です。クロサバフグの毒は、日本産の物であれば無毒とされていますが、産地が南シナ海産のものとなると、筋肉や卵巣、肝臓に毒があるという報告が為されているので注意が必要です。
シロサバフグについて
次にシロサバフグという種類について、クロサバフグと同様に記していきます。こちらも食用として広く使われている、サバフグの中では有名な種のうちの一つです。外見やその他白フグに関する様々な情報を記載します。
シロサバフグの基本的な特徴
シロサバフグもサバフグ全般と同様に太平洋側の沖合、その全般において釣り上げることが可能です。クロサバフグよりも沿岸性があるため、一般の方が釣り上げるとしたらこちらの方がメインとなるでしょう。国内の漁獲量においても、その個体数が多いためか最も上がっています。外見は背と腹に小さな棘があることが特長です。
シロサバフグの毒性
シロサバフグには毒があるのでしょうか。答えは、シロサバフグ自体は無毒です。なので、食性があるといえます。しかし、後に述べるドクサバフグと外見が非常に似ているといった問題点があることから食用として用いるにも制限がかかってしまっています。
ドクサバフグについて
最後はドクサバフグという種類について。この種は大変危険ですから、必ずその特徴をおさえておきましょう。ここでは、その生息域や外見の特徴といった情報はもちろん、ドクサバフグの毒に関する知識も記していきます。
ドクサバフグの生息域
サバフグに中には猛毒を持つドクサバフグという種があります。もともと日本近郊では揚がっておらず、東シナ海や南シナ海、インド洋や南アフリカ共和国において見つかっていた種でしたが、ここ最近では日本近郊でも生息が確認されており、一般の海釣りの方も注意が必要な魚となってきました。
ドクサバフグの外見の特徴
ドクサバフグは体の背と腹の両方に小さなとげがあることが特長です。この棘は背びれの付け根まで全体にわたっています。そして、一般に食用として用いられる白サバフグと外見が非常に似ています。そのため、この見分けには高度な専門的知識が必要です。
ドクサバフグの毒性
ドクサバフグの毒は猛毒で、食べれば食中毒を引き起こし、最悪の場合は死に至るものです。毒は卵巣や腸、肝臓といった臓器の部分のみでなく、皮膚や筋肉にも毒が含まれています。よって、素人調理は危険として、注意勧告が多行われています。一応、食性はありますが、調理には免許が必要です。