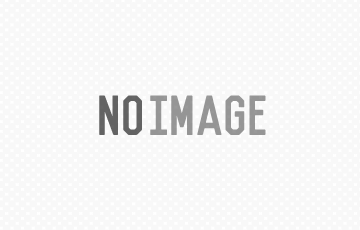カワムツってどんな魚?
みなさん「カワムツ」ってご存じですか?「聞いたことがあるようなないような。。。」そんなあまり耳慣れない魚だと思います。それもそのはず、「カワムツ」はあまり市場には出回らない食卓では稀少な魚です。けれど、場所によっては身近な川魚だったりします。今回は、そんな「カワムツ」について、生態や釣り方、飼育方法をとおしてさまざまな姿をご紹介します。
カワムツの分類
「カワムツ」は、コイ目コイ科ダニオ亜目カワムツ属のお魚。コイのお仲間になりますが、コイほどにはおおきくならず、成長した大人の「カワムツ」でだいたい10-15cmほどです。コイと同じように淡水で生息する川魚です。
名前の由来
「カワムツ」は、その名の通り「川(カワ)に棲むムツ」という意味で、これは琵琶湖地方での呼び方が通称として一般化しました。つまり、海に棲む「ムツ」に対して川に棲む「ムツ」。ただ、地方により呼ばれ方はばらつきがあり、岡山県新見市、高梁市などの地方では「ドロムツ(泥ムツ)」、福岡県久留米市付近では「ヤマソバヤ」、他にも「アカムツ」、「ハヤ」、「モツ」、「シロムツ」など数え切れないくらいの呼び名があります。「カワムツ」が日本古来から私たちの身近に棲み、親しまれてきた証しですね!