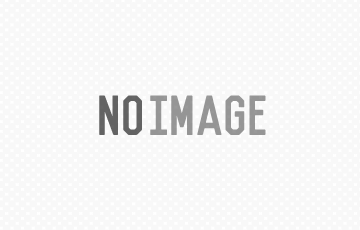潮目の特徴・見方
潮目とは、違う種類の海水同士が、海の中でぶつかり合う時に起きる現象です。実は、一口に海水と言っても、『流れの速さ、水温、塩分の密度』が場所によって違うと言われています。海水同士がぶつかることでプランクトンが集まったり、海中の酸素が多くなるという特徴があります。
プランクトンが多い
潮目にはプランクトンが多く存在すると言われています。海水同士がぶつかると、その衝撃で海底に沈んでいた砂が舞い上がります。その砂の中にプランクトンのエサになる栄養素がたくさん含まれているので、潮目はプランクトンが増えやすい環境になっていると言われています。
海中の酸素が多い
潮目では、海水同士がぶつかることで激しい流れが生まれ、海中に酸素が取り込まれやすい状態になっています。海中の酸素が増えることで、魚がエラ呼吸をしやすくなるので動きが活発になると言われています。
潮目で魚が釣れる理由
潮目付近の海中はプランクトンと酸素が多いので、プランクトンをエサにする小魚が集まりやすい環境になっています。また、その小魚を狙ってくるフィッシュイーターと呼ばれる中型大型の魚も集まりやすく、潮目には様々な生物が集まりやすい条件が整っています。
小魚にとって最高のエサ場
潮目には、プランクトンをエサとするアジやイワシなどの小魚が集まってきます。暖かい海は、魚の生息数がおおいので、エサになるプランクトンが少ないと言われています。逆に、冷たい海は魚の生息数が少ないので、プランクトンが豊富と言われています。
潮目は暖かい海水と冷たい海水がぶつかる場所でもあるので、小魚にとって冷たい海に行かなくてもプランクトンをたくさん食べられる最高のエサ場になっているのです。
フィッシュイーターにとっても最高のエサ場
潮目には、プランクトンに集まってくる小魚をエサにするブリ、カツオ、シイラ、マグロ、スズキなどのフィッシュイーターと呼ばれる中型から大型の魚も集まってきます。小魚を食べる魚にとっても、潮目はエサが集まりやすい最高のエサ場になっているのです。
潮目が生まれるメカニズムを徹底解析
沖合だけでなく、防波堤や砂浜などでも潮目は発生します。しかし、場所によって潮目が発生する条件が変わってくると言われています。では、釣り場ごとの潮目の発生条件はどういったものなのでしょうか?釣り場ごとの潮目の発生条件をまとめてみました。
堤防の潮目
堤防の近くには港があることが多く、船の往来が多いのが特徴です。この船の行き来によって、沖に出ようとする海流が発生します。それに対して、沖から岸に向かってくる海流とぶつかることで潮目が生まれることがあります。
防波堤の潮目
大きな波を防ぐために、テトラポットやコンクリートの壁を使った防波堤を設置してある場所では、防波堤にぶつかり跳ね返って沖に戻ろうとする海流が発生します。その海流と、沖から防波堤に向かってくる海流がぶつかり潮目が生まれることがあります。
砂浜の潮目
砂浜では、浜にぶつかって沖に戻ろうとする海流と、沖から岸に向かう海流がぶつかって潮目が生まれることがあります。砂浜で発生する潮目は、砂浜から遠いことが多いのでヴェーダーなどを着用する必要があります。
沖合の潮目
温度や塩分濃度の違う海水の大きな海流同士がぶつかり潮目が生まれます。ぶつかったときの衝撃が大きいので波が荒くなることが多いと言われています。
潮目がよめる人、よめない人の違い
釣り場で周りが誰もつれていないのに、どんどん魚を釣り上げている人を見たことありませんか?もしかしたら、その人は潮目を読んでいた可能性があります。潮目がよめる人、よめない人では釣果に大きな差が出てきます。では、潮目がよめる人、よめない人の違いはいったいどこにあるのでしょうか?
時間の使い方・効率が良い
潮目がよめる人は、潮目を中心にポイントを絞り、魚が集まりやすいところを探りながら仕掛けを入れています。そのため、適当に仕掛けを入れている人と違い、魚が釣れる可能性が高くなり釣果が上がりやすくなります。また、潮目は時間によって移動するため、潮目がよめる人はそれに合わせてポイントを移動させることでさらに釣果を上げています。
マキエのロスが少ない
潮目がよめる人は、潮目に仕掛けを入れ周辺にマキエをまきます。マキエは潮目にとどまることを知っているからです。しかし、潮目がよめない人は、潮目と関係のないところに仕掛けを入れ、マキエをまくので、潮の流れに乗ってマキエは潮目の方に行ってしまいます。せっかく集まった魚はコマセと一緒に潮目に移動してしまうので、仕掛けに魚を寄せるために常にコマセをまき続けなければいけなくなります。
知らないと損する潮目の探し方
潮目を探すには、海面の動きを見ることが大切です。潮目は流れの違う海流がぶつかり合う場所なので、水同士の色が違ったり、別々の場所から流れてきたゴミなどが浮かんでいたりします。こういったポイントを探し出すことで潮目を探すことができます。