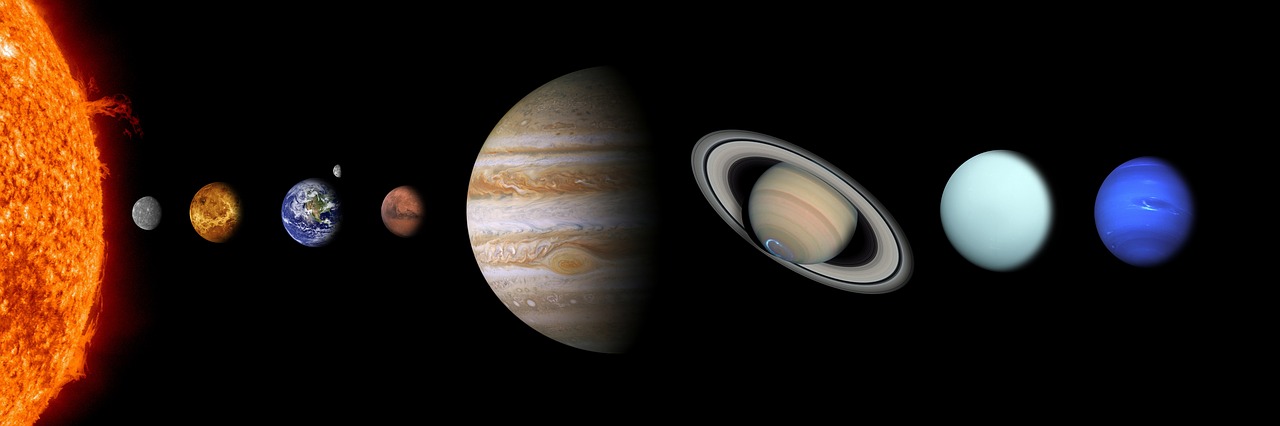人々から恐れられていた「太歳」ですが、現在では祭られていた建物が中国で実際に残っています。それが「太歳殿」です。ここでは昔皇帝が「太歳神」の災いを恐れ、1532年に建てられて旧暦の12月24日と正月に祭祀を行ったとされています。現在では「北京古代建築博物館」として一般公開されていますので、中国に訪れた際は一度行ってみてはいかがでしょうか?
Contents
日本での「太歳」
さて、ここまで中国で言い伝えられている「太歳」について触れました。しかし「太歳」は中国だけでなく、日本でも言い伝えられているエビソードがあります。日本では「太歳」はどのようなことを意味していたのかを見てみましょう。
陰陽道で方位神となる
中国の占術や天文学などの知識にプラスされ、様々な影響によって日本独自で発展されたものが陰陽道です。この陰陽道によると「太歳」は8人の方位神の中の一人として位置づけられています。
太歳神と凶方位
陰陽道によれば太歳神は木星の精であり、四季の万物をつかさどる神といわれています。木星の精と呼ばれることから、樹木や草など自然に関する性格なので、太歳神のいる方角太歳神の方角で伐採や草刈りをすることは言語道断とされています。
また、太歳神は陰陽道の8人の方位神の中でも君主的な立場という面もあります。そのため訴訟や談判などの争い事は疫災にあうともいわれています。
太歳神と吉方位
では太歳伸は悪い神様なのかというとそんなことはありません。木星の精なので太歳神いる方向で樹木や草木等を植えることはよいこととされています。また、貯蓄することや結婚、家を建てること、商談の取引、就職などいったお祝いごとに関することは良いことといわれています。
2019年の「太歳」は?

DarkWorkX / Pixabay
ここまで「太歳」の方位について知ると、2019年の「太歳」の凶方位が気になりますよね。2019年の凶方位を載せておきますので、皆さんにとって良い年に過ごせるよう2019年の凶方位を載せておきます。
2019年の凶方位は「北北西」

OpenClipart-Vectors / Pixabay
2019年の干支は「亥」ですので太歳は「北北西」となります。ですのでこの方角への引っ越しや伐採などは絶対に避けましょう。特に今年は「北北西」で凶方位としてやってはならないことを行うと、かなり悪いことが起こる可能性が大きいとされているので要注意です。
大見出し:太歳と干支の関係って?

Quique / Pixabay
太歳が生まれた理由として干支が関係しています。太歳がどのようにして生まれたのかそのルーツについてご紹介します。
歳星紀年法で起こった周期の崩れ
歳星紀年法は木星の位置に基づいて記録されたもので、中国の戦国期に使われていました。木星は12年かけて一周すると天文暦学についてのところでご説明しましたが、一周するときには天の赤道に沿って西から東へ12等分に区切って一周します。これを十二次といい、その時の位置で年を記録していました。
このことから木星は年を表す星とされ「歳星」と呼ばれるようになります。しかし時が流れるにつれ、星座の位置がずれてきてしまいました。これにより周期が崩れていったのです。
歳星紀年法に対する太歳紀年法
そこで今度は新たな紀年法が用いられるようになります。それが木星を使った太歳紀年法です。冒頭で「太歳」は十二支と反対にまわり、この2つが鏡像に関係することから「太歳」ができたとご紹介しましたが、この「太歳」から十二支の位置づけをして、年を記録するようにしたのです。
中国で発見された?

OpenClipart-Vectors / Pixabay
ここまでの話を聞くと「太歳なんて歴史上でしか存在しないものじゃないか」と思ってしまうかもしれません。しかし、実は中国で「太歳」が発見されたというニュースがあり、話題となりました。一体何が発見されたのかご紹介します。
中国で発見されたというニュースが飛び込む!

OpenClipart-Vectors / Pixabay
ニュースが飛び込んできたのは2015年12月のことでした中国の北東部で農夫をしているワン・チェンドーさんが自宅近くの山でそれを発見したとのことです。重量はなんと70キログラムもあり、クリーム色がかった奇妙な物体・・・そう「肉霊芝」とも呼ばれるあの「太歳」だったのです。
ワンさんが1キロ日本円にして3500円で販売したところ注文が殺到、なんと100万円以上の売上となりました。
実際に食べた人がいるって本当?

congerdesign / Pixabay
「太歳」は非常に希少なもので見つからないのが現状なのですが、実際に食べた人が過去にいました。「山海経」と書物に、肉のような味がすると実際に記録に残っているそうです。しかし現代では「太歳」販売されているものの、中には偽物もあるので興味を持って買うときには注意しなければなりません。
実際に見つかった太歳を徹底調査

OpenClipart-Vectors / Pixabay
不老不死として言い伝えられている「太歳」ですが、ミステリアスでどんなものなのか気になりますよね?ここでは「太歳」がどんなものなのか詳しく追及します。
どんな見た目なの?
まず見た目ですが色はクリーム色がかっていたり黒っぽいものもあります。写真を見てみるとわかりますがまるで肉の塊のようで過去の歴史で奇妙な存在として見られているのもうなずけます。
傷をつけてもすぐにふさがる!?

ElasticComputeFarm / Pixabay
もう一つ奇妙な存在として見られる理由があります。それが「太歳」がもつ再生能力です。先ほど太歳を発見したワンさんのお話をしましたが、この方が発見したのち「太歳」を冷水につけると、たちまちちぎった部分が再生されたのです。不老不死といわれる理由がお分かりいただけると思います。
太歳の正体は…?
見た目やその再生能力・・・すべてにおいて謎に包まれている「太歳」ですがその正体はなんなのでしょうか?諸説ありますが体を移動させて微生物を食べる動物的特徴と胞子で繁殖するという植物的特徴をもった新種の菌であるというのが一番優良な説とされています。
今なお息づく「太歳」の伝説を、あなたは信じますか?

SplitShire / Pixabay
様々な意味がある「太歳」についてたくさんご紹介しましたがいかがでしたか?共通して言えることは「太歳」はとても神秘的な存在で、謎の深いものだということです。中国を訪れるチャンスがありましたら是非この「太歳」を思い出していただけますと幸いです。
昔からあるということで共通しているものに「即身仏」というものがあります。ミイラとの違いなどご存知でしょうか?興味がある方はこちらも御覧ください。