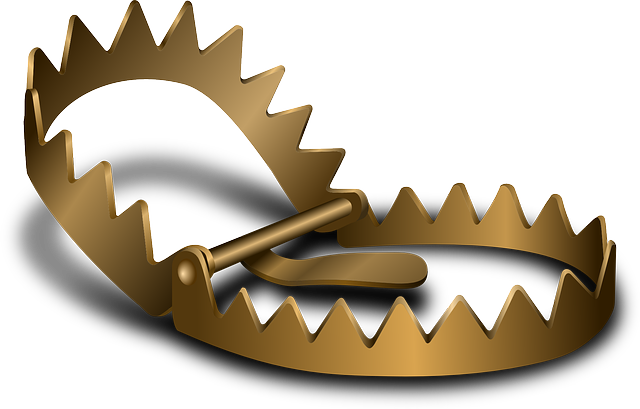トラバサミとは?使用禁止の危険な罠

Efraimstochter / Pixabay
『罠』という言葉で思い浮かぶものは、どんなものでしょうか?「落とし穴」や「ハニートラップ」などでしょうか?では、『痛い罠』という言葉からは、どんなものを思い浮かべるでしょうか?
『痛い罠』という言葉からは、「ギザギザの歯を持ったトラバサミ」を思い浮かべる方も多いでしょう。手軽に思いつき、手軽に扱えるため、使用が禁止された現在でも違法な利用を行う人が多いのです。
トラバサミは、主に狩猟に使われる罠です。形や大きさなどによって威力が変わり、様々な種類があるため、捕らえる獲物の大きさや、捕らえた後の目的の違いによって使い分けることができます。
トラバサミは動物狩猟用のバネ式の罠
トラバサミは、中央部分についている板と連動して、左右についている刃が動く仕組みになっています。板の上に重みがかかると、左右の刃が閉じてしまい、刃に挟まれた獲物は抜け出せません。
罠の仕組みにはバネが使われているため、左右の刃は素早く閉じ、刃の形や大きさによっては骨を粉砕する威力があります。簡単な仕組みの罠ですが、正しい外し方を知らないものは刃を開くことができません。

JenDigitalArt / Pixabay
主に狩猟に使われる罠ですが、「鼠用の小さく威力も弱いトラバサミ」や「熊用の大きく威力の強いトラバサミ」など、獲物によって使い分けができるほど様々な種類があります。
威力に大きく関わる『刃』にも様々な形があります。「獲物に刺さるギザギザの鋸歯形の刃」や「緩衝材がついた獲物に優しい刃」など、用途によって『刃』の形も大きく違っています。
日本でのトラバサミ使用・販売は原則禁止

出典:PhotoAC
2007年(平成19年)法律の改正によって、日本でのトラバサミを利用した狩猟は禁止猟法となり、トラバサミの販売も規制され、購入には行政の許可が必要になりました。
使用するためには、「狩猟者登録証」または「捕獲許可証」を取得する必要があり、購入する際には、「狩猟者登録証」または「捕獲許可証」を提示する必要があります。
日本でのトラバサミの使用が許可されるケース

cocoparisienne / Pixabay
「学術研究」「有害な鳥獣による被害の防止」「特定鳥獣の個体数調整」など、環境大臣が許可したケースに限りトラバサミを利用した捕獲ができます。
「有害な鳥獣の捕獲」ではトラバサミに標識をつけ、設置者の名前や設置位置を示さなくてはなりません。標識をつけずに設置した場合は違法になります。
「緩衝材がついた獲物に優しいトラバサミ」での捕獲に限り、環境大臣の許可が下ります。トラバサミを使わなくても捕獲できる動物しかいないことを理由に、自治体が許可しない場合もあります。
事業の妨げとなる害獣の駆除には規制が適用されない

Alexas_Fotos / Pixabay
「モグラなどの害獣が農業従事者の事業の妨げとなり、駆除や捕獲が必要な場合」や「農業従事者以外でも、鼠などの害獣が事業の妨げとなり、駆除や捕獲が必要な場合」は、トラバサミに関する規制は適用されません。
2017年(平成29年)度の鳥獣による農作物への被害は、「金額約164億円」「農作物約47万4千t」「面積は約5万3千ha」と、減少傾向にあるとはいえ高い水準のまま、農業従事者を苦しめ続けています。
「鹿」「猪」「猿」による被害が全体の約70%を占めています。どの鳥獣も小型ではないため、トラバサミで捕獲する場合は環境大臣の許可が必要になります。
80ヶ国以上の国でトラバサミの使用が禁止されている

Clker-Free-Vector-Images / Pixabay
80ヶ国以上の国がトラバサミの使用を禁止していますが、皮革産業が盛んな「アメリカ」「オーストラリア」「ロシア」「カナダ」や、発展途上国などでは毛皮生産用の猟具として使われ続けています。
EU(欧州連合)では使用を原則禁止としていますが、EU(欧州連合)に加盟するオーストリアでは、制限付きで使用を認めています。
使用禁止の国も使用可能な国から毛皮を輸入している矛盾も

Gaertringen / Pixabay
EU(欧州連合)はトラバサミの使用を1990年代に原則禁止としましたが、その罠を使う「アメリカ」や「カナダ」などの毛皮を現在でも輸入しています。
アメリカでは毛皮の需要が少ないため、捕らえられた動物の毛皮は大半が輸出されています。年間で5万匹を超える動物達が命を奪われ、その毛皮はトラバサミの利用が禁止されている欧州などの高級店へ送られています。
トラバサミの違法利用で動物にも深刻な被害が

ChristopherPluta / Pixabay
トラバサミは「環境大臣が許可したケース」や「事業の妨げとなる害獣の駆除」以外の目的で使用すると違法になります。トラバサミを違法に利用した場合は刑罰が科せられます。
「害獣の駆除」は、鼠などの小さな動物に使う場合のみが対象となります。小さな動物用のサイズではなく、猫くらいの大きさの動物にも使用できるサイズを設置してしまうと、違法になる場合が多いです。
私有地に設置された罠は撤去されることが少なく、強制的な撤去も難しいという現状から、違法利用された罠が放置され、近隣に住む人や動物に被害を与えています。
トラバサミで猫が負傷

出典:PhotoAC
現在の日本では、庭や家庭菜園を野良猫に荒らされないように、トラバサミを設置する一般の民家が増えています。一般の民家なので、「事業の妨げとなる害獣(鼠などの小型の動物)の駆除」が目的ではありません。
一般の民家では「野良猫の侵入を防止すること」を目的として設置するケースが多く、小型用ではなく中型のものを利用しています。「緩衝材がついていないトラバサミ」を違法に設置している民家もあります。
許可を得ている場合でも、標識をつけずに罠を設置すると違法になりますが、一般の民家では「トラバサミが設置してある」と表示するのみで、設置位置を明確にする標識をつけていない違法利用が多く見うけられます。

super-mapio / Pixabay
「野良猫の侵入を防止すること」を目的として設置するケースが多いため猫への被害が多く、そのまま死亡してしまうケースもあります。標識のない罠の違法な設置は、子どもが挟まれる危険もあります。
東京都の公園に設置されたトラバサミに猫が挟まれ、そのまま死亡している姿が発見されたケースや、飼い猫が罠に掛かり、挟まれた際に負った怪我が原因で、数時間後に死亡したケースも報告されています。
トラバサミを違法に販売している業者もいる

出典:PhotoAC
使用・販売が規制される前は、ホームセンターなどの小売店でトラバサミが店頭販売されていました。現在はトラバサミを扱う小売店が少なくなり、誰もが容易く店頭で購入できる状況は改善されました。
現在でも、違法な販売を続けている業者も存在します。通信販売のサイトでは千円台のトラバサミが違法に販売されており、求めやすい価格なため、通信販売に抵抗がなければ容易く入手できてしまいます。
トラバサミを使用することの問題点

betexion / Pixabay
トラバサミは、選び方や使い方次第で非常に残酷な罠となり、動物や人間に大きな被害を及ぼす可能性があるため、各国で使用に対する批判の声があがり、80ヶ国以上の国が使用を禁止しました。
トラバサミの問題点①無差別に被害が及ぶ

出典:PhotoAC
トラバサミは、罠についた板を踏むと自動で獲物を捕らえる仕組みになっているため、獲物の選別ができません。板を踏むのが人間や絶滅危惧種であっても罠は作動するのです。
罠は獲物に気づかれない場所に設置するケースが多いため、人間が掛かってしまう可能性もあります。「ギザギザの刃がついたトラバサミ」や「大型動物用のトラバサミ」に掛かってしまうと酷い怪我を負うでしょう。
「大型動物用のトラバサミに掛かった猪の肘関節が、腱と皮のみで繋がっている状態だった」という害獣駆除業者の話もあります。大型動物用の刃は、人間の足の骨も粉々にしてしまうほどの威力があります。
トラバサミの問題点②掛かった生物に苦痛を与える

Clker-Free-Vector-Images / Pixabay
トラバサミは、自動で獲物を捕らえる仕組みの猟具であり、罠の外し方を知らないものは安全に逃げることができません。誰かが気づいて助けてくれるか、足を切断して逃げ出すまで苦痛が続く罠なのです。
「学術研究」などの目的で設置した罠なら、頻繁に人が確認に訪れるため苦痛な時間は短くて済むでしょう。しかし、一般の人が設置した罠の場合、数日間確認に来ないことも考えられます。
設置した本人が忘れてしまった場合、誰かが気づいて撤去しない限り罠は放置されたままになります。そんな罠に捕らえられた獲物は、足を切断して逃げ出すか、死ぬまで苦しむことになります。
トラバサミを発見した時に取るべき対応

出典:PhotoAC
トラバサミの利用が原則として禁止となった現在の日本でも、違法な設置をしている人がいます。罠の違法な設置は森林や山の中だけではなく、都会の公園や団地の中でも発見されています。
日常生活の中で、気づきにくい場所に設置されたトラバサミを発見した場合の対処法や、自分や動物が罠に掛かってしまった場合の正しい外し方をご紹介します。
お店で違法に売られていた時はお店に是正要望を

LeeChandler / Pixabay
日本での利用が禁止されている猟具を、店頭に並べて売るのは違法です。トラバサミを店頭で陳列して売っている小売店を発見した場合は、小売店に要望を伝えましょう。改善が見られない場合は警察に通報しましょう。
違法なトラバサミ使用を発見したらすぐに警察に通報

出典:PhotoAC
設置されたトラバサミを目撃した場合は、見やすい場所に標識がついているか確認しましょう。住所・氏名などの記載がない標識は、役目を果たせていないため、標識のない罠と同じ扱いになります。
標識がついていない罠(全ての罠が対象)の利用は違法です。違法な利用の場合は、すぐに「警察」や「鳥獣保護員または鳥獣保護の担当者(都道府県・市町村)」に通報しましょう。
野生の鳥獣を違法な利用のトラバサミで捕獲した場合、「1年以下の懲役」もしくは「100万円以下の罰金」という刑罰の対象となります。
トラバサミに掛かった動物を発見したら警察に通報し保護

出典:PhotoAC
動物が掛かったトラバサミを目撃した場合、先ずは「警察に通報」しましょう。次に「鳥獣保護員に通報」します。鳥獣保護員の所在が分からない場合は都道府県庁に連絡し、取締りの担当の人に来てもらいましょう。
「証拠を保全」しましょう。動物が虐待された証拠の写真を撮り、トラバサミを証拠物件として警察に押収してもらいましょう。最後に「動物を保護」しましょう。動物病院に連れていき、必ず診断書をもらいましょう。
「動物虐待の罪」で罠の設置主を告訴する場合や、被害を受けた動物の飼い主が「器物損壊の罪」で罠の設置主を告訴する場合には、虐待や損壊の証拠と診断書が必要になります。
トラバサミに掛かってしまったら正しい外し方を

出典:YouTube
罠に掛かってしまった動物を発見した場合や、自分が罠に掛かってしまった場合、正しい外し方を知らずに無理に引き抜こうとすると大変危険です。正しい外し方を知り、安全に罠を解除しましょう。
外し方を知るには、罠の仕組みを知る必要があります。トラバサミには、刃の付け根部分に「板バネ」と呼ばれる部品がついており、「板バネ」を踏むと刃が開く仕組みになっています。
「板バネ」から足を離すと、もう一度刃が閉じる場合もあるため、「板バネ」を踏んだまま挟まっている部分を抜きましょう。単純な仕組みなので、正しい外し方を知っていれば、安全に罠を解除できます。
トラバサミの由来とその歴史

出典:YouTube